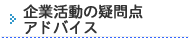KIGYO支援情報会員 / メールマガジン見本
LLPによる起業のメリット・デメリット
Limited Liability Partnership(LLP:有限責任組合)という新しい企業の形態を規定する、有限責任事業組合契約法が2005年8月から施行され、注目されている。
LLPは英国で発祥し、米国で発展した。形態の名称から判るように有限責任のパート名シップである。日本の民法上の組合は無限責任であるが、LLPは有限責任である。
LLPの最大のメリットは、何といってもその税制にある。一般に、法人組織にすると、法人に法人税、法人事業税、事業主に所得税と、2段階で課税される。これに対してLLPでは、LLP自体には課税されず、出資者に直接課税される。また、LLP自体が赤字なら、損失を経費として出資者個人の所得から差し引ける。つまり。税金はLLPにかかるのではなく、各組合員(partner:出資者)にかかる「パススルー課税(pass through tax)」と呼ぶ方式がとられる。
しかし、税務当局もこのパススルー課税を野放しにしているわけではない。2005年度の税制改正で、一定の枠を設けてきた。LLPの各出資者が所得税(法人の場合は法人税)の計算時に経費として各年度に計上できる金額に上限を儲け、出資額までとした。これに対しては、ハイリスクが予想される事業にLLPを使おうとする利点が、損益通算を制限することで失われるという批判がある。
もう一つの利点は、組織や損益配分を出資者間の契約で自由に決められることである。取締役も監査役も不要、損益配分は出資額の多寡ではなく役割や貢献などを配慮して決めることができる。
さらに、出資者でもある組合員の責任は、limited liabilityの言葉からもわかるように、株式会社の株主同様、出資額の責任の範囲に限られる有限責任である。民法の組合員が無限責任を負わされるのに比べ、起業しやすい。LLPが株式会社と組合の「いいとこどり」といわれるゆえんである。LLPは資金はないが技術や専門知識を持っているという事業主に向いている。
LLPは、中小事業者ばかりではなく、大手企業も活用し始めた。東日本旅客鉄道(JR東日本)、NTTドコモ、NTTデータの三社により、電子マネー(スイカ)の利用を促すLLPを設立する(日本経済新聞より)。
LLPのデメリットとしては、LLPは利益の内部留保ができないことから、永続的な事業には向かないことがあげられる。また、出資者が抜けるときの財産の再配分が難しいなど注意しておくべき点もある。
いずれにしても、組織の多様化で起業の選択肢が増えることは良いことであるといえよう。